こんにちは!!
9月の研修会内容のご報告をさせて頂きます。
9月8日(日)に定期研修会が行われましたご報告です。
この日は台風15号の接近が危ぶまれていた日でもありましたので、遠方の新幹線組の先生たちは来られませんでした。
都内の上空も雲の流れがかなり早くて、雨が土砂降りだったかと思うと、急に晴れたりして、まさに台風のお天気でした。
当日は交通マヒのことも考えて、研修会の時間も15時までと短縮になりました。
この台風での被害は関東で大打撃でした。
現在もですが、被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興を願うばかりです。
最近の気候変動の激しさは全く予想ができないので、自然の脅威をただただ恐ろしく感じるばかりです。
そんな中でも我々は自己研鑽の歩みを止めることはできませんので、この日もしっかり取り組みました。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
朝の“医事寸言”は、福島志乃先生のお話でした。

今夏の京都で行われた夏期学術研修会が終わって帰宅した翌日、ぎっくり腰になってしまったそうです(; ・`д・´)
先生は研修会で講師もされていたのですが、志乃先生を治療した院長先生曰く「血虚によるぎっくり」だったようです。
血をガッツリ消耗してしまうくらい、先生は夏期学術研修会にエネルギーを注いでいたんですね(^O^)!!!
院長の治療により事なきを得たとのことでしたが、そのエネルギーを参加された方々もたくさん吸収したと思います♪♪
本題は、志乃先生が自分で“圓鍼”を製作したお話でした。
普段は銅と銀とカーボンの圓鍼を臨床で使い分けているそうですが、治療家年数を重ねて来たら自分の鍼が欲しくなり、製作しよう!!と考えたようです。
そこで選んだ素材が“水晶”とのことでした。
水晶を選んだ理由は、熱の伝導率が良いことだそうです。
御徒町に水晶を求めに行ったこと。
水晶には色々な種類があるということ。
水晶の削り方などの作業工程。
臨床で利用した際の話。
などなど。
先生の感覚だと、水晶の圓鍼の合う人は肺虚体質の人に合う気がすると言っていました。
※作り方に興味のある方は、先生の治療院のHPに掲載してあるとのことですので覗いてみて下さい♪♪
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
入門部は、今村光万先生が漢方鍼医会のテキストに沿って、
“脾の生理・病理・治療”について講義をして下さいました~(*^-^*)♪♪
脾胃の特徴のお話を簡潔にわかりやすく説明して下さいました。
<脾>
〇気血津液を作って、全身に巡らせる働きをしている。運化作用。
〇脾で作った気血津液を肺に持っていく。肺から全身に巡らせる。昇清作用。
〇土気は中庸性を持っている。全身のバランスが偏らないようにしている。
〇脾で作った気血津液を一気にばらまかず、全身のバランスをみて調整していく作用。
〇融和性。自分の為に働くというより、相手の為に働く。
このような働きを求める時に、陰経の兪土穴や陽経の合土穴を選穴すると良い。
他。
<胃>
〇身体に入った飲食物を腐熟して消化するが、その働きがないと脾は気血津液を作り出せない。胃の働きは脾にとってとても重要です。
〇胃の働きのエネルギー源は、心の陽気をもらっています。心の陽気が各臓器に行って働くと相火という名前になります。心の相火が脾に移動して、脾から心の相火を胃に渡して働いてもらっています。胃にはいつも熱がある状態。熱がある限り胃は働けます。
冷たいものを胃に入れ過ぎると陽気が抜けて胃の働きが低下します。
他。
まだまだたくさんあるのですが。
内容は盛りだくさんなので、かなり抜粋して書いてあります(; ・`д・´)
脾胃の生理・病理は(他の臓腑も重要なのですが)、特に気血津液の生成に関わるので、特に大事な項目ですよね!!
※講義内容は、当会のテキスト『新版漢方鍼医基礎講座』第3項脾・胃の生理と病理の内容に先生がプラスαして下さっていますので、詳細を知りたい方はテキストを入手することをおすすめ致します。
研修部発表は、
第一席「精神疾患」山口尚文先生です。
精神疾患には、発達上の問題や統合失調症、うつ病や双極性障害、パニック障害、性機能障害、薬物依存、知的障害やパーソナリティ障害など、様々な症状を呈する状態があります。
西洋医学において心身に関する医学分野が切り開かれたのはごく最近のことですが、漢方医学では二千年以上前から心身一如の病理観がとられ、治療に応用されてきました。
性格や生い立ち、ストレスの影響などを受け、思考・感情・行動というものは人それぞれであり、精神疾患であるか?そうでないか?も、とても曖昧なものだと思います。
また日々の生活において、身体をどうして心を安定させるかいかに大切であるかを強く感じます。
人間が生きていくために重要な部分である“精神”。
“心”を東洋医学的に把握するために生理観・病理観の認識を深めていきたいと思います。
それからは、山口先生の治療現場でのお話。
治療に携わる中には、統合失調や軽度のうつ症状の患者様など様々な方がいます。
ただ、精神疾患という病は深い病気であると思います。
(中略)
色々なお話と、山口先生自身が胸痛に見舞われた際のお話をしてれたりしました。
これは自分で割いたサンマの刺身の寄生虫が悪さをしていたということでしたが(^_^;)
感情(五志)と五蔵。
身体の変調は五志との深い関わりがあるので、治療の際は掘り下げて患者様自身を観察しなければならないということを改めて考えさせられました!!
感情(五志)と五蔵の関わりが書いてある古典をピックアップして話して下さいました♪
(下記に記載したものです。)
『霊枢』
本神篇 第八
口問篇 第二十八
天年篇 第五十四
本蔵篇 第四十七
『素問』
上古天真論篇 第一
生気通天論篇 第三
陰陽応象大論 第五
湯液醪醴論篇 第十四
脉要精微論篇 第十七
宣明五気篇 第二十四
挙痛論篇 第三十九
調経論篇 第六十二
※後は当会のテキストも。
↑これらを参考に~(*^-^*)♪♪
第二席 「虚実」荒川雄一郎先生です。
以前も同じテーマで研修部でお話したことがあります。
今日はその時の内容をベースに虚実の基本的な考え方から、夏期研でも話題になっている陰陽調和の手法、脈の虚実、四十八難など最近会で取り上げられていることを整理していきたいと思います。
鍼の治療では虚実に対して補瀉が行われます。
それが全てです。
手法による補瀉を行うために虚実とは何なのか?と考えることは必要不可欠な問題です。
虚実の意味が定まらなければ、補瀉の意味も定まりません。
古典において虚実という言葉の示す意味は、幅広いです。
“古典あるある”と言いましょうか、条文の中で同じ言葉を使っていても違う意味を指している場合もあります。
理解を深めるためにも陰陽関係を知っておかなければいけません。
なので、まず陰陽の復習をしていきます(‘ω’)ノ♪♪
と。いうことで。
資料やテキストをもとにがっつり復習しました!!
そして虚実へ
※当会テキスト『漢方鍼医基礎講座』参照。
陰陽について。
虚実や陰陽については、基本中の基本ですから復習をしっかりした感じになりました
(*^-^*)!!
古典の内容と絡めたものと、荒川先生の普段の臨床で感じることを加えて判り易かったですね。
陰陽調和の手法も噛み砕いて説明してくれていたので、頭の中で想像して考えやすかった講義でしたね♪
そして研究部発表、
第1席「気圧変動による身体のホメオスタシスと季節の治療の相関性について」
猪上竜剣先生
毎年冬になると私の友人は腰痛になる。そして、毎年秋に頭痛の患者様がよく来る。
その原因は冷えかと思いきや、必ずしもそうとは限らない。
毎年くる秋の気候は暑い時も寒い時もあり、気温と無関係の場合もある。
しかし、腰痛や頭痛は毎年秋から冬かけて多く発症する。
近年現代医学でも天候よって同じ症状を起こす「気象病」として認知されるようになった。
晴れの日になると虫垂炎の患者様が増えたり、雨天の日はリウマチや喘息症状が増えたりする。
その要因は、気圧変動により自律神経機能が過剰に活動することからである。
私の友人や患者様の症状から「気象病」と考えられる。
いつも私達の身体に纏っている空気が圧をかけて病を誘発しても不思議ではない。
季節の病を既に古典医学書には記されている。その中で運気論は気候と身体の関連性を多く表現されている。
その中で診断法に「天道地理の変化を明らかにして、身体の体型や気の虚実を診ることができる」と重要性を記されている。
「天道地理の変化」を気圧変動の視点で、邪正抗争の均衡を失うことは、気圧により自律神経機能を乱されてしまったこと関連性がある。
よって、気圧変動・身体の自律神経機能の相関性を明快にして、季節の治療に如何に活かることを考察する。
気温だけでなく、気圧も身体の変化が顕著に出ると本にも書かれていたので、それも邪の中のひとつではないかと私は思い、気圧の方から邪を考えてみました。
以下の三つのポイントから説明します。
1、気圧変動と自律神経機能の解説。
気象のことと、現代の医療の人たちは気圧に対してどう対処しているのか?
2、古典医学書から運気論よる診断と治療法。
3、気圧変動よる自分なりの治療例。
皆さんは“気圧”のイメージをどう捉えていますか?
雨がしとしと降っている時は低気圧で、逆に良く晴れている時は高気圧?
というような認識でしょうか(*^^*)?
“気圧”は一気圧1013hPaと言われています。
高気圧の特色というのは、空気が多いんです。
上空から空気が下にズシンと私達や自然のところに空気の圧がのしかかって来ます。
空気の流れも下に流れて外に噴き出すような感じです。
※北半球・南半球では回転が変わります。
そのうち空気が圧縮して来るので温度が少し高めになったりします。空気がどんどん押して来るので、水滴などの水関係のものは上に上がり難くなります。
低気圧の特色は、空気が少ないです。
そして、空気がどんどん上に上がって行きます。
水分も上に上がって行って気温が低くなり、それが雲となり、雨となります。
私たち人間も自然の中で、常に“圧力”と共に存在しています。
何かの文献でかいてあったのですが、私たちは常1m四方で10tくらいの空気がのしかかっているらしいです。
しかし、生活をしていて物理的に空気が重いと感じたことはありませんよね?
それはどうしてだと思いますか?
(中略)
というお話から色々深まり、他の先生方からの言葉も加わり、脳外科手術の際は圧を気を付けていることや、赤ちゃんは低気圧の際は頭が膨張するなどの意見もあり。
恐らく治療されている方々や、普通でも脳溢血の後遺症などでお辛い方が天気で半身の痺れや痛みが増すとか、頭痛持ちの方が天気による変化に敏感ということも良く耳にします。
今回猪上先生の話は、古典も絡めつつ、気圧の観点からの治療の考え方だったので大変面白かったですね(^O^)♪
研究部第2席は、
「現在の私の行っている治療」 中里康章先生

当初は刺激の強弱を実際の治療にてどの様に使い分けていくべきかと言う事について発表しようと思っていましたが、もう少し範囲を広げて現在私が行っている治療という観点でお話していきたいと思います。
以前から邪正論や陰陽調和、オーソドックスな経絡治療の様な治療法、考え方を学んできたのですが、答えが出ないケースがあるんじゃないかと思っていました。
治療の答えを持っているのは“患者さん”が持っているのだと思います。
なので、教科書的にとか季節とかで進めていくのも良いのですが、あくまでも私の場合は
患者さんのからだの変化を診る、そして治療するのだと思っております。
私の影響を受けた先生は、加賀谷先生もなのですが私の母親が野口整体で40年間鍼灸マッサージ師だったのですがそれで治療してきて、ぎっくり腰なんて5分くらいで治してしまう腕前でした。
私自身も子供の頃から病院に行った記憶も無くて、風邪をひいた時も薬も飲まず、ただ「水を飲んで寝ていなさい」と言われました。
野口先生は『風邪の効用』という本を書いていますが、読んだら“なるほどな!”と思いました。
そういうことも加味して、私が普段どのように行っているかをお話したいと思います。
私の好きな俳優で、ブルース・リーという方がいるのですが、その方が“エンターザドラゴン(燃えよドラゴン)”という映画の中で少年に言う言葉があるのですが
「Don’t think feel.(考えるな!感じるんだ!)」
古典理論も、このツボの位置がここだからではなくて、その患者さんからどういうものを発しているかを感覚として“感じる”ということ。
これが大切なのではないかと思っております。
私は気を鍼で動かすという観点から治療しておりますので、それを念頭に置いております。
治療概念は、経脈絡脈上の反応点(経穴)を媒体として、鍼という道具を持ち、反応点(経穴)から発している気を動かすことにより経脈絡脈を通して、五臓六腑の陰陽の調和を図る。
これがベースになっております。
アプローチ対象はあくまでも“気”です。
よって施術は服の上からでも可能です。
診断に関しましては色んなことを試したり、研究したりしましたが今現在私が行っているのは胸腹部です。
古典の甲乙経にもありますが、募穴と要穴の気の反応点、及び脈診を使用します。
反応点に関しては、私は“手かざし”によって気の有無を確認しております。
手かざしというのは、手をかざして、気は感じるものですからあくまでも手をかざした時に手に感じる気を重要視します。
これを胸腹部のどこの位置に一番気の反応が出ているか?
これに関しては夢分流でいうところの腹部の研究をしたり、実際の臓腑の位置などを色々研究してみましたが、今のところやはり一番良いと思うのは募穴鍼です。
自分が思うところの診断&治療をしていると呼吸が変わってくるのを感じます。
(中略)
質疑応答まで“気”に関する質問がたくさんありました!!
実際“気”を感じたり、見たり、治療に応用したりするには?というような内容を中里先生の日々の臨床体験の一部を聞かせて頂きました。
気を操る?のは訓練でできるものだ!!と。
その他も興味深いお話が聞けて良かったです(*^-^*)♪♪
※毎回書きますが、研修会の発表内容は当会の会報誌に掲載されるので、ブログではチラ見くらいを載せさせて頂きます。
全部をブログで書くことはできませんので(^_^;)
もっと詳しく知りたいな~という方は、一度会に足を運んでみてください!!
お問い合わせはお気軽に!!
お待ちしております。
広報 鈴木りゑ
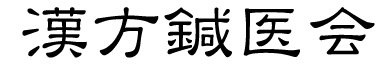
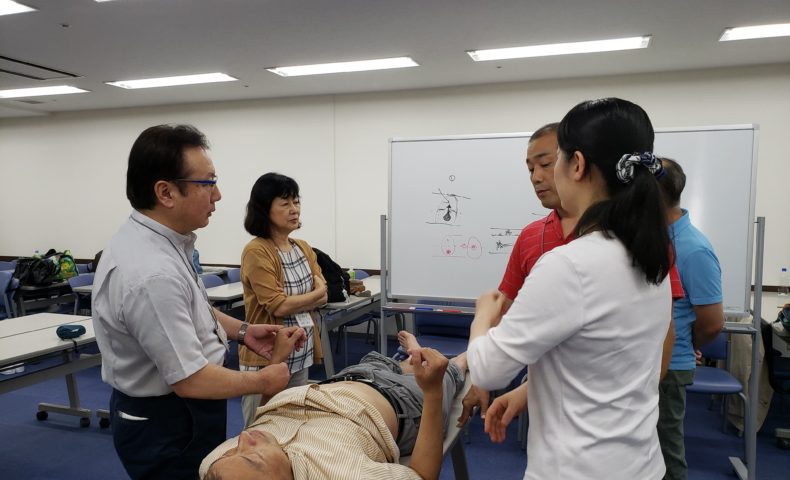
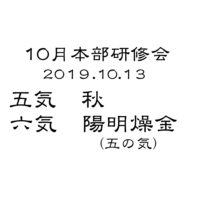
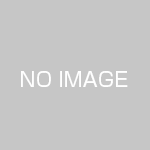






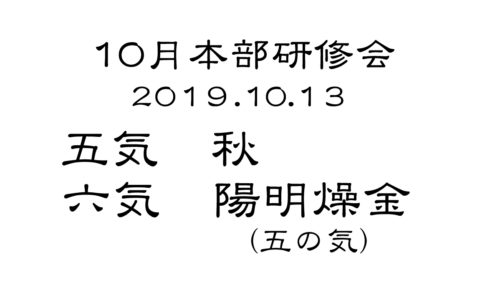
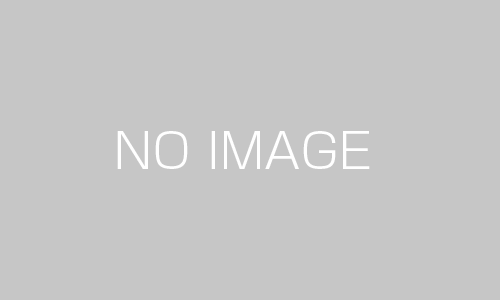
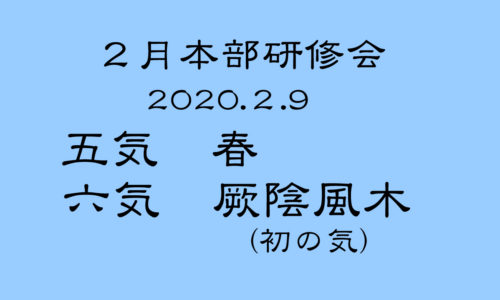
この記事へのコメントはありません。