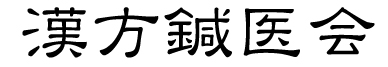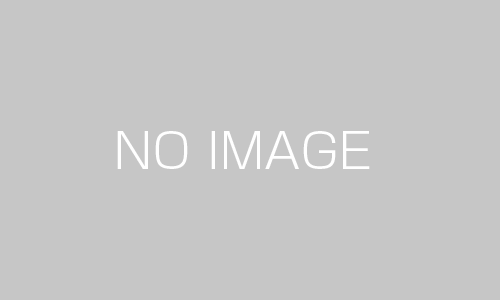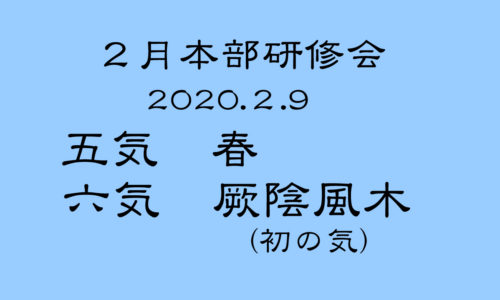令和5年度事業計画
【1】学術研修計画
(1)入門部研修計画 入門部担当 水戸尚子
令和6年度は入門部2年目になります。1年目は「臓象論」を中心に、五臓六腑の生理と病理、病症と治療法を学んでいきました。2年目では「脈診」「診察法」「病因論」「選穴法」を学び、より実践的な臨床を身につけていきます。実技では接触鍼の補瀉法、脈診法を深め、小里式による実技を行い、それぞれご自身のイメージした治療法を身につけて行きます。
(2)研究部研修計画 研究部担当 新井芙美法
研究部の今年度のテーマは「季節の中での漢方はり治療」「接触鍼の補瀉法」になります。「季節の中での漢方はり治療」はここ数年にわたる年間テーマとなり、臨床実技や各自臨床の中でも定着してきました。今年度はさらに令和4年度の研究テーマでもあった「陰陽脈診」を季節の治療法にからめ、今年一年間の座学を通して実践を重ねていきます。また、午後の臨床実技では治療前に「接触鍼の補瀉法」を行い、それぞれの心構えや姿勢造りを再確認させていきます。例年10月に行っていた外来講師講演は、今年度は4月午後に設定しました。松塾学術担当理事である松田博公先生を講師に迎えお話をうかがいます。鍼灸ジャーナリストであるとともに黄帝内経研究家である先生ですので、興味深いお話が多々聞けることと思います。臨床家である我々とは違う視点のお話を聞くことで新たな学びを得、新年度への最初の1歩としていきましょう。新たな試みとしては、地方漢方の先生をお招きし研修会で行われている学術についてお話していただきます。今年度は6月に三河漢方の森野弘高先生に「小児鍼」について発表していただきます。森野先生は長らく「小児鍼」にたずさわり、書籍の出版や各地での講演など大変精力的に活動されています。本部では取扱いの少ない専門性のあるテーマですが、学術面に加え実際の臨床現場での様子など、具体的なお話が聞けることと思います。また翌7月には森野先生の話をもとに意見交換会を行います。各先生の感じた印象や臨床にどう生かすかなど自由な意見を交わしましょう。
2024年度 年間カリキュラム
(1)入門部
4月
10時〜 第31回漢方鍼医会 定期総会
10時30分〜 会長講演 漢方鍼医会会長 新井敏弘
5月
午前:「診察法」 講師:巻田明宏 司会:
午後: 実技
6月
午前: 森野先生「小児鍼」
午後: 実技
7月
午前:「振り返り」
午後: 実技
8月
休み
9月
午前:「病因論」 講師:浅井利浩 司会
午後: 実技
10月
午前: 「選穴法」 講師:谷内孝暢 司会
午後: 実技
11月
午前:「脈診」 講師:新井敏弘 司会
午後: 実技
12月
午前:「季節の治療」 講師:福島志乃 司会
午後: 実技
2月
午前:「標治法」 講師:吉田清隆 司会
午後: 実技
3月
午前:「養生法」 講師:水戸尚子 司会
午後: 実技
(2)研究部
4月
10時〜 第31回漢方鍼医会 定期総会
10時30分〜 会長講演 漢方鍼医会会長 新井敏弘
5月
午前:「外来講師講演の振り返り」 講師:関野玲子 司会:青島崇裕
午後:実技
6月
午前: 森野先生「小児鍼」
午後:実技
7月
午前:「意見交換会(小児鍼)」 講師:学術部 司会:吉田清隆
午後:実技
8月
休み
9月
午前:「未定」 講師:福島志乃 司会:吉田陵
午後: 実技
10月
午前:「未定」 講師:中里康章 司会:吉田清隆
午後: 実技
11月
午前:「未定」 講師:田村佳津子 司会:細沼弘
午後: 実技
12月
午前:「演題未定」 講師:斉藤太誉 司会:浅井利浩
午後: 実技
2月
午前:「未定」 講師:大高達雄 司会:加耒ひなこ
午後:実技
3月
午前:「未定」 講師:新井康弘 司会:吉田陵
午後:実技
入会・聴講案内